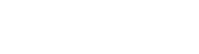2022年10月7日(金)~ 10月28日(金)
<このページ下部に表示される申込フォームよりお申し込みください。
※全4回の講座申込になります。>※「おとなのためのサイエンス講座」お申し込みご検討のお客様へ
本イベントは開講予定で準備を進めておりますが、新型コロナウイルスへの対応に関する状況により、延期、もしくは中止となる可能性がございます。
ご参加を楽しみにされているお客様には大変申し訳ございませんが、予めご理解・ご了承のほどお願い申し上げます。
第1回 山手台地の風景
10月7日(金) 13:30~15:00
見慣れた景色も地学を通して見ると違った風景となります。例えば山手線は山手台地と縄文時代の海進で削られた山手台地の崖の下を通ります。等々力渓谷は山手台地の地下の様子を見ることができる貴重な渓谷です。渋谷駅前のスクランブル交差点は、渋谷川の“川底”にあたります。
第2回 東京低地帯の風景
10月14日(金) 13:30~15:00
東京下町と呼ばれる地域は、昔の利根川や荒川が削った谷に、新しく海が侵入して埋め戻した東京低地帯です。かつての荒川の流路のまわりに自然堤防と呼ばれる微高地がありました。この微高地に寺院などが建てられました。浅草寺もそのひとつです。
第3回 下総台地の分水界を越える
10月21日(金) 13:30~15:00
JR武蔵野線は低地帯を抜け下総台地の縁を通っています。下総台地にあがると、台地上の河川は東京湾側に流れる河川と太平洋側に流れる河川に分かれます。その境界線を分水界と言いますが、それはわずかな高低差でできています。その先にある利根川の上流域は、徳川幕府による東遷の舞台でした。
第4回 筑波台地の風景
10月28日(金) 13:30~15:00
筑波台地には谷津(谷戸)の地形が発達しています。谷津は雨水や湧水によって幅広く削られてできた地形のことです。なぜこのような地形が発達するのでしょうか。また筑波台地上には多くの調整池が作られています。調整池の必要性は、筑波台地をつくる地層と関連があります。 ※全4回の講座申込になります。>
※全4回の講座申込になります。>※「おとなのためのサイエンス講座」お申し込みご検討のお客様へ
本イベントは開講予定で準備を進めておりますが、新型コロナウイルスへの対応に関する状況により、延期、もしくは中止となる可能性がございます。
ご参加を楽しみにされているお客様には大変申し訳ございませんが、予めご理解・ご了承のほどお願い申し上げます。
第1回 山手台地の風景
10月7日(金) 13:30~15:00
見慣れた景色も地学を通して見ると違った風景となります。例えば山手線は山手台地と縄文時代の海進で削られた山手台地の崖の下を通ります。等々力渓谷は山手台地の地下の様子を見ることができる貴重な渓谷です。渋谷駅前のスクランブル交差点は、渋谷川の“川底”にあたります。
第2回 東京低地帯の風景
10月14日(金) 13:30~15:00
東京下町と呼ばれる地域は、昔の利根川や荒川が削った谷に、新しく海が侵入して埋め戻した東京低地帯です。かつての荒川の流路のまわりに自然堤防と呼ばれる微高地がありました。この微高地に寺院などが建てられました。浅草寺もそのひとつです。
第3回 下総台地の分水界を越える
10月21日(金) 13:30~15:00
JR武蔵野線は低地帯を抜け下総台地の縁を通っています。下総台地にあがると、台地上の河川は東京湾側に流れる河川と太平洋側に流れる河川に分かれます。その境界線を分水界と言いますが、それはわずかな高低差でできています。その先にある利根川の上流域は、徳川幕府による東遷の舞台でした。
第4回 筑波台地の風景
10月28日(金) 13:30~15:00
筑波台地には谷津(谷戸)の地形が発達しています。谷津は雨水や湧水によって幅広く削られてできた地形のことです。なぜこのような地形が発達するのでしょうか。また筑波台地上には多くの調整池が作られています。調整池の必要性は、筑波台地をつくる地層と関連があります。 ※全4回の講座申込になります。>
- トップ
- 『江戸から常陸野へ-風景から学ぶ身近な地学-』